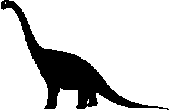 気候モデリング分野
気候モデリング分野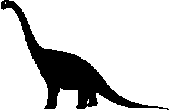 気候モデリング分野
気候モデリング分野気候は決して一定ではありません。今から1万年前の氷河期にはヨーロッ パや北アメリカ大陸北部は厚い氷床に覆われていました。最近は エルニーニョ現象 など自然の気候システムの変動に加え、温室効果ガスの増加による「 地球温暖化」とそれに伴う気候変化が世界中で 問題になっています。 このようなさまざまな気候の変化の機構を 気候モデルを使った実験によって明らかにしてゆくことが本センターの使命 ですが、気候モデリング分野では、それとともに気候システム全体を通してのエ ネルギー源である太陽放射と地球放射の研究、それに簡略モデルによる気候シス テムの振舞いの研究を行い、大気・海洋両モデルを結合した本格的気候モデル実 験の基礎作りを行っています。
英語版へ 研究テーマ
研究テーマ◆ 大気モデルと海洋モデルを結合した気候モデルの開発
◆ 簡略化大気・海洋結合モデルによる二酸化炭素増加とそれに伴う地球温暖化の研究
◆ 地質時代の気候変動に関する基礎的研究、特に氷期・間氷期サイクルの機構の解明
◆ 気候システムのエネルギー収支、特に放射収支の研究
◆ 衛星リモートセンシングによる雲等の全球場の動態とその気候影響の研究
 気候を計算する
気候を計算する気候は気温、降雨量、風など大気の状態や大気現象の長期平均の現れです。従って、気候を計算するには大気モデルで季節による日射の変化を与えて何年間かの計算を行い平均を取れば良いと思われます。ところが、大気の長期的平均状態は、大気そのものより、その下にある海水面や陸地面の状態(積雪の有無、土壌水分量)によって強く影響されますから、気候を計算するには海水温や陸地面の状態が分かっていなければなりません。一方、海水温や陸地面の状態は、例えば、寒気の吹き出しで海水が冷えたりするように大気によって支配されます。結局、気候を計算するには、大気・海洋・陸地面の全ての状態を相互作用も考慮して一度に取り扱う必要があるということになります。 大気大循環モデルでは海水温に観測値を用いて海洋の影響を取り入れ、海洋大循環モデルでは観測から得られた平均風によってひき起こされる海流を計算しましたが、気候モデルでは大気と海洋の両モデルを結合し、相互に矛盾の無いように計算を進めます。観測値を用いず手放しに計算するだけに正しい結果を得ることは大変に難しく、従って、気候モデリング分野での第一の目標は良い気候モデルを開発することです。気候モデルができれば、それを用いて海陸分布や二酸化炭素濃度などが現在と異なる地質時代の気候の推定をしたり、人間活動によって温室効果ガスが増えてゆく時、気候がどう変わるかのアセスメントを行ったりできます。しかし、現在、大気、海洋各モデルが未完成なので両者を結合したモデルによる実験は95年以降に行います。
 簡略モデルによる地球温暖化の研究
簡略モデルによる地球温暖化の研究大気・海洋結合モデルを用いて人間活動によって放出されたCO2がどのように海洋に吸収され海洋中で循環するのか、また、CO2濃度の上昇によって熱放射がさまたげられたとき、余分の熱がどのように海洋に吸収され温度上昇が遅れるのかなどが調べられています。しかし、大気・海洋結合モデルはまだ不十分な点が多く、また計算量が膨大になるため、世界中で数えるほどしか実験が行われていません。 そこで、大気・海洋結合系を思い切って簡略化し、海洋を深さ方向一次元で表しCO2や熱の輸送・拡散を取り扱って地球温暖化の進行の概略を調べています。実は、1990年にまとめられた「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」の報告でも同様のモデルで温暖化の将来予測を行っていたのですが、CO2の吸収と熱の吸収を扱う海洋モデルにくい違いがあり、どちらも海洋中の輸送過程を表すのに問題があります。そこで、両者の欠点を取り除いた2層湧昇拡散モデルによってこれらの問題を研究しています。
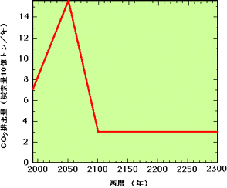

図1 人間活動によるCO2排出量が将来左図のようになるとした時(当面は増加し21世紀半ばから新エネルギー実用化で減少、2100年から一定)の大気中CO2濃度の将来予測(右図)
 放射とリモートセンシング
放射とリモートセンシング気候システムの様々な部分の温度を現在の値に保ち、様々な現象を引き起こしている駆動エネルギーが、太陽から降り注ぐ太陽放射と宇宙空間に散逸してゆく赤外放射であることはいうまでもありません。したがって、太陽放射が空気分子・雲・エアロゾル(微粒子)によってどのように散乱・吸収されるかのか、また、地表面や大気中の温室効果ガス・雲・エアロゾルが、赤外線をどのように放出したり吸収したりするのかを把握することは、気候の成り立ちを知る上で大変重要なのです。そこで、当分野ではこのような様々な放射過程を気候モデルの中で再現する研究も行っています。例えば、地球温暖化を引き起こす温室効果の再現などがその例です。 ところが、このような気候モデリングを実証するためには、実際の雲や水蒸気などの動態を把握する必要があります。そのためには全球規模の観測が可能な人工衛星による地球観測が重要な研究手段になります。例えば、図2に示したような雲の大規模な変質は、気候変動の一要因ともなりますが、現在のリモートセンシング手法を用いればこれらの変質の実態を明らかにすることができます。そこで、人工衛星データの解析による放射収支、雲や水蒸気などの全球規模の動態把握もモデリングと平行して行っています。

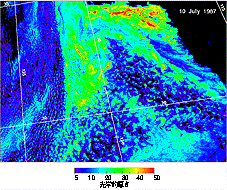
図2 カリフォルニア沖の層積雲のリモートセンシング。光学的な厚さ(右)と雲粒の等価半径(左)。大陸(各図の左上隅の黒色部分)から吹き込むび微粒子を多く含む気団の影響を受けると、雲は厚くなり、また雲粒も小さくなります。人間起源の大気汚染も同様な過程を通して雲を厚くし、気候に大きな影響を与える可能性があります。
