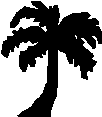 気候解析分野
気候解析分野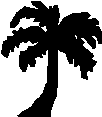 気候解析分野
気候解析分野気候解析分野では、長期間の全球的な地上、高層大気、海洋、衛星等の観測データを用いて、実際の気候システムがどのような時間・空間構造を持って変動しているか、大気−海洋−陸地面の間の相互作用はどの様に行われているかを明らかにします。また、世界各地で起きている異常気象の要因の分析を行います。さらに、これらの結果と各種の理論モデル、数値モデルによって得られた結果と比較することによって、モデルの改良に役立てます。
英語版へ 研究テーマ
研究テーマ◆ 気候モデルの検証と改良
◆ 地球温暖化現象の検出
◆ 気候システムの年〜数十年変動の解明
◆ 組織化された熱帯対流活動の特徴の把握
◆ 中・高緯度大気中の長周期変動の解明
◆ 異常気象の要因の分析
 気候変動の実態解明
気候変動の実態解明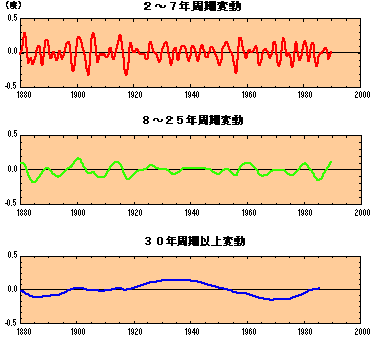
全球平均地上気温は最近100年の間に約0.5℃上昇していますが、その要因として二酸化炭素等温室効果気体の増加が考えられています。しかし、実際の気温変化にはその他の自然の要因によると思われる数年〜数十年の時間スケールで変動する成分も含まれています。図1は、約100年間の全球平均地上気温のデータに適当な時間フィルターをかけて2〜7年周期、8〜25年周期、30年以上の周期の変動を取り出したものです。この内、2〜7年周期の変動はENSO(エルニーニョ・南方振動)の影響を強く受けたものであることがわかっていますが、他の長い周期の変動要因は今のところわかっていません。地球温暖化現象の検出のためにも、このような数年〜数十年の変動の実態とそのメカニズムを明らかにすることが重要です。
 異常気象の要因分析
異常気象の要因分析
1993年は約40年ぶりの顕著な冷夏となり、北日本、東日本の夏の間の平均気温が平年に比べて2℃近く低く、米作などの農作物に甚大な被害が出ました。図2は1993年7月中旬〜下旬の地上天気図と上空約5000メートルの偏西風の流れ(赤線)を示したものです。このような地上・高層観測データの解析から、1993年の大冷夏は、(1)太平洋高気圧の勢力が弱かったこと、(2)北海道の北でオホーツク海高気圧が長期間停滞したこと、によると思われます。(1)に関しては、日本の南の熱帯太平洋の対流活動や海面水温の変化が関係していたものと考えられます。また、(2)に関しては、偏西風が日本上空で大きく南北に蛇行し停滞する現象(ブロッキング現象−図2の赤線)が現れたことと関連しています。気候解析分野では、このような異常気象の要因を分析するとともに、エルニーニョやブロッキングなど異常気象を引き起こす現象のメカニズムの解明を行います。
 衛星観測を用いた熱帯対流活動の解析
衛星観測を用いた熱帯対流活動の解析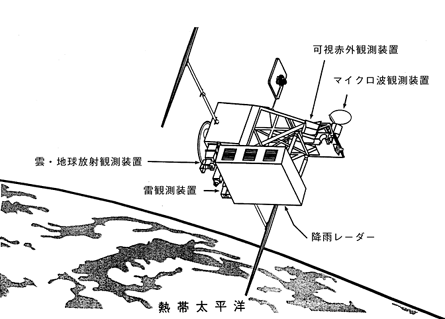
前述のように、熱帯域の対流活動の時間的空間的変化は、日本など中・高緯度の天候に大きな影響を与えています。しかし、熱帯域はそのほとんどを海洋で覆われているために、対流活動の振舞いを明らかにするには通常の地上からの観測だけでは極めて不十分です。近年、気象衛星による可視、赤外、マイクロ波の観測データを利用して、対流活動の変動を明らかにしようとする研究が大きく進展してきました。その結果、熱帯域の対流は、数十キロメートルから数千キロメートルの様々な空間スケールにまとまっており、各々の空間スケールによって異なった振舞いをすることが明らかになってきました。これまでの衛星観測では主として対流域の雲頂付近の情報しか得られませんが、1997年には衛星に降雨レーダーを搭載して宇宙から熱帯の降水システムを観測しようとするTRMM(熱帯降雨観測衛星)が打ち上げられる予定で、対流活動のより詳細な内部構造が明らかになることが期待されています。本センターはTRMM計画実現に向けて積極的に参画して行きます。
