気候モデルとは
そこに自然がある。
われわれは地球に暮らしている。地面に立って見上げれば空があり、遠くには海が見える。昼には太陽が照り、海や陸の水分が蒸発、凝結することで、空には雲ができる。時には雨や雪を降らせる。雨や雪は水として地上に蓄えられ、あるいは河川を通じて海に流れ出る。日本は中緯度にあって、夏は暑く、冬は寒い。暖かい地方には広葉樹が、寒い地方には針葉樹が生える。世界には砂漠や氷河といった人類にとって過酷な環境も存在するが、陸地には生存に適した豊穣の地も多い。これらはすべて気候を「語る」自然界の現象である。
気候には、われわれの生活圏から離れた海洋内部や上空約10kmより高い領域(成層圏)も重要である。成層圏にはオゾン層があって生物を有害な紫外線から守り、大西洋から太平洋の海洋内部を巡る深層循環は高緯度域を温暖に保つ役割がある。また、自動車の排気ガスなどの大気汚染物質や火山の噴煙、近年話題の二酸化炭素も気候を形作る要素として重要である。図1に、このような「気候システム」を模式的に描いた。
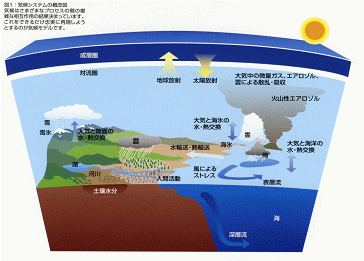

自然には物理が宿る。物理には数式が宿る。
このように多岐に渡る現象を内包する気候は、現代科学、特に物理学によって多くが理解されている。風や潮の流れは物理学の基本法則であるニュートンの法則を流体に適応することで理解される。気温や水温の変化は、熱に関する物理法則によって理解される。雲の形成や氷の生成は、水の相変化に関する原理から理解される。空気も水も地球に居留まるという質量保存則や、圧力、密度、温度の3者の関係式といったものを含めると、気候を司る多くの部品が理解できる。つまり、南風に乗って暖かく湿った空気が運ばれて、気温が上昇し、その空気は上昇して冷やされ水分が凝結して雨を降らせる。このような当然の話を、物理法則によって定量的に見積もる術を得たのである。
これらの法則のほとんどは微分方程式という数式を使って表現される(下)。これらは非常に複雑であるが、基本的に未知の変数の数と方程式の数が一致している連立方程式と考えてよい。当然、地球が一日で一回転していることや、太陽光線の強さや、地球の大きさといった基本的な情報は、定数として与えられている。これらの式は気候を司る方程式だけあって、様々な気象現象を説明できる。たとえば、温帯低気圧や移動性高気圧が成長しながら、日本付近を繰り返し通過するという現象も式の解に含まれる。これらの式の性質は大気海洋科学の中で十分探求され、よく理解されている。


数式は近似される。近似された数式をコンピュータが「解く」。
上記の数式は、紙と鉛筆では決して解けない。コンピュータの力を借りることになる。そこで、コンピュータが解けるように、下の図のように地球をある間隔の網で覆い、それぞれの網の中の代表値だけを計算するという、数式の近似を行う。その代表値について、ある初期の値から出発し、未来の値を次々に求めていく。しかし、現在ある世界最高水準のコンピュータの性能を如何なく発揮したとしても、気候の問題を考えるために100年間分の値を計算しようとすると、網目の間隔は大気では100km程度が限界である(図2)。この限界によって、方程式に含むことが出来なくなった現象を、何らかの形で補う必要がある。つまり、100km程度の規模の状況から数kmの現象を推測して、そのような小さい規模の効果を100km程度の規模の現象に反映させなければならない。これをパラメタリゼーションという。特に、雲を介した対流運動(強い上昇気流が狭い範囲で起こる)や地面近くの乱流(空気や水の乱れ)は、大規模な現象に影響する重要な過程である。パラメタリゼーションの方法論はさまざま提案されているが、物理的な根拠が薄弱なものも多い。このような不確定性が、地球温暖化予測の不確定性を生じさせる大きな要因である。
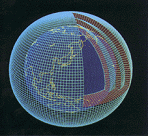
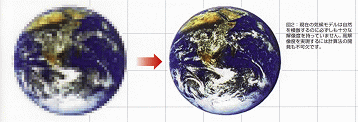
さて、これらは具体的には、どのように実現されるのだろうか?コンピュータはたとえ変数と方程式だけあっても、それだけでは何もしてくれない。方程式や条件式を機械が理解できるプログラムに焼きなおす必要がある。下にはCCSR/NIES/FRCGCモデルで実行されるプログラムの先頭部分を示す。初期のデータを入力し、このプログラムを実行してはじめて将来の気候の姿が出力データとして現れる。気候モデルとはまさにこのシステムを指す。この気候モデルを用いて、地球温暖化や異常気象について実験し、その成果を社会に還元することで、気候モデルに「魂」が入ることになる。(文章:岡、稲津;図版はCCSRパンフレットおよびホームページより引用;式とプログラムはモデル本体より抜粋)