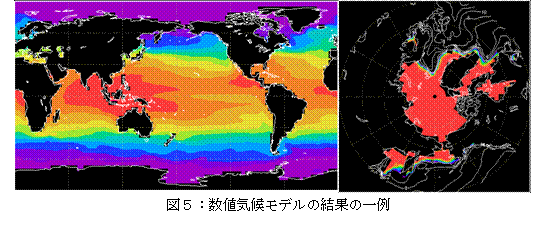海洋深層大循環から気候の成り立ちを考える
羽角 博康(東京大学気候システム研究センター)
気候と海洋深層大循環 −気候システムの一部としての深層海洋−
人の気候に対する意識はもともと、日々の過ごしやすさであるかとか、農耕に適した環境にあるかなど、人の生活環境に立脚しています。科学的な定義をするならば、人の意識する気候とは、陸上地表面付近の気温・湿度・風系・降水量といった大気の物理的指標をもって特徴づけられるものと言うことができます。この陸上地表面付近の大気の物理的状態は、それ自身のみではなく、はるか上空の大気の状態から、陸上の植生や雪氷分布、そして海洋の状態とも密接に関連して決められています。そのような意味からは気候というものをもっと広い枠組みから捉えることができ、陸上地表面付近の大気の物理的状態と密接に関連する要素の総体を指して「気候システム」と呼び、気候システム全体の状態に対して気候という語が用いられます。気候システムは通常、物理的特徴によっていくつかの構成要素に分けて考えられます。分類の方法は一通りではありませんが、代表的な例は大気(表層・対流圏・成層圏などにさらに分けて考えることもあります)・海洋(海面混合層・温度躍層・深層など)・雪氷(大陸氷床・山岳氷河・積雪・永久凍土・海氷)・陸面(植生・土壌・河川)のような分類です(図1)。この中で深層海洋は、人の直接の関心の対象としての気候から最も遠い所にあるものと言えるでしょう。
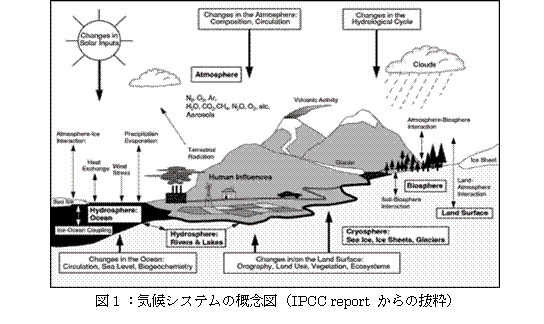
身近なところでは日々の天気の変化にとっても大気と海洋の相互作用は重要なものですが、大気との相互作用に直接関わるのは海洋の状態のうち海面水温だけと言えます。しかしながらもちろん、海面水温はその下にある海洋の状態から影響を受けて決まっています。海洋の構造を鉛直方向に見ていくと、大部分の地点において、上から、海面から数十メートル深まで温度・塩分がほとんど一様な海面混合層、数百メートル深にある温度が急激に変化する温度躍層、そしてその下の深層と、温度の特徴的構造から分けることができます。海洋は大気と比べて大きな質量を持ち、それに伴って大きな力学的・熱力学的慣性、そして大量の溶存物質を持っています。それによって、一般的に言って海洋は気候の時間的あるいは空間的変化を穏やかにする働きを持っています。海洋全体の質量や熱容量は大気のそれと比べて千倍以上あり、もし海洋全体が海面の状態に即座に応答したとすると、大気の日変動や季節変動は非常に小さなものになってしまいます。実際には、短い時間スケールを持つ気候現象に対しては先ほどの鉛直方向に見た海洋の分類のうちの一部のみが実質的に応答するようになっています。海面混合層は日々の天気の変化から季節変動といった数年程度以下の時間スケールの海面水温の変化、ひいては人の意識する気候の状態の変化に大きな影響を及ぼします。また、エルニーニョ現象に代表されるような数年から数十年の時間スケールを持つ気候変動では、温度躍層より上の上層海洋が応答し、その応答こそがそのような気候変動を形作るための支配的要因となっています。
一方、深層海洋はと言うと、百年から千年の時間スケールを持つ気候変動、あるいはそれよりさらに長い時間スケールを持つ氷期−間氷期サイクルといった現象を考える場合に重要となります。また、長時間平均で見た気候の状態を決めるのにも深層海洋の存在は本質的です。後ほど詳しく述べますが、深層海洋の循環に伴う熱輸送がもし存在しなかったとしたら、低緯度は現実よりもはるかに高温に、そして高緯度は現実よりもはるかに低温になってしまいます。すなわち、日々の天気の変動には深層海洋は影響しませんが、そもそも地球上の多くの場所が人の居住できる気候状態にあるということ自体は、深層海洋の影響なしには考えられません。また、先ほど海洋の存在は気候の時間的・空間的変動を穏やかにする働きがあると述べましたが、これも後ほど述べますが、場合によって海洋深層大循環は短期間に劇的に変化し得ると考えられており、気候システム全体に大規模な変化をもたらす要因ともなり得ます。したがって、長時間の平均として見た場合の気候(気候システム全体としてのみならず、人が普段意識する気候という意味でもです)の状態がいかに決定されるかにおいて、そしてそのような平均的な気候の状態の大規模な変化(氷期の到来・終焉など)をコントロールするものとして、深層海洋は気候の状態形成と深く関わっているのです。
海洋深層大循環の成因と実態
先ほど述べたとおり、海洋は鉛直方向に見た場合にいくつかの層に分けられます。また、水平方向に見た場合には、太平洋・大西洋など、陸地または海底地形によって区切られたいくつかの海盆に分けられます。この上層と深層をつなぎ、そして海盆間をつないで全海洋を巡る循環が深層海洋大循環です。この深層海洋大循環は、非常に単純化して言えば水平熱対流と同じ原理、すなわち、海面において海水の密度変化をもたらす外力が水平方向に不均一であることによって生じます。海水の密度は温度と塩分で決まり、したがって海面での熱交換や淡水交換(降水など淡水流入による塩分希釈、および蒸発による塩分濃縮)が密度変化をもたらす外力となります。これによって高い密度を持つ領域(深層水形成領域)で海水が表層から深層へ沈み、それが深層を巡りつつ表層へと上昇し、表層を深層水形成領域に向かって流れるという循環を構成しています。海洋物理学においては、このように密度の不均一に起因して生じる循環のことを熱塩循環と呼びます。
現在の気候の状態においては、深層水形成が生じている場所はグリーンランド海・ラブラドル海・南極大陸の周囲の大陸棚上といった、極めて限られた領域であることが知られています。この狭い領域で沈み込んだ深層水が残りの広い領域で湧昇するという形で現在の深層海洋大循環が存在します(図2)。氷期などの現在と大きく異なる気候状態においては、深層水形成場所や形成量が現在とは大きく異なり、それがそうした気候の状態を維持する一因になっていたと考えられています。また、人為起源二酸化炭素排出による地球温暖化の予測においては、この深層循環がどのように変化するのかがひとつの焦点となっています。
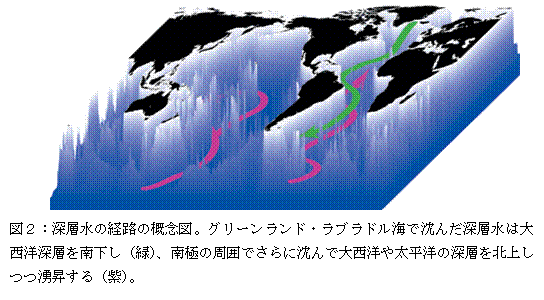
深層水形成には多くの素過程が複雑に作用していますが、その根源にある過程は深層対流と呼ばれるものです。これは水柱が海面から冷却されるなどによって上層の密度が下層よりも大きくなった場合に、その重力不安定を解消するために生じる現象で、そのうち海底までもしくは千メートル程度以深の深層に達するものです。この深層対流は十キロメートル程度という非常に小さい水平スケールで生じる局所的な現象で、生じている箇所も数箇所にすぎないのですが、言わばそれが全球深層大循環をコントロールしています。現在の深層水形成領域は主として高緯度海洋にあり、そこでは海面での熱交換は冷却、すなわち深層水形成を促進する方向に働いています。一方、海面での淡水交換は淡水化、すなわち深層水形成を阻む方向に働いています。これら反対方向に働く外力と海洋循環の微妙なバランスのもとに深層水形成領域や形成量は決められています。また、これらの深層水形成領域は海氷の存在領域と重なっていますが、海氷の存在は大気−海洋間の熱交換に対して断熱材として働く一方、海氷中には海水と比べてわずかな塩分しか取り込まれないため、海氷の生成・融解は海面塩分を変化させる外力として働き、深層水形成の過程をさらに複雑なものとしています。これら様々な過程のうち、どの要素が深層水形成のどのような側面にどの程度の大きさを持った影響を与えるかはいまだ十分に理解されておらず、それを知ることが海洋深層大循環の物理的特性を解き明かすためのひとつの鍵となります。
気候システムの熱収支という観点から
簡単のために、まずは海洋深層大循環を熱的な側面だけから考えてみます。高緯度において生じている深層水形成は海面における上からの海水の冷却を原因とし、それはすなわち海洋がこの領域で熱を失っていることを意味します。これを大気側から見ると、大気が熱を獲得していることになり、それによって高緯度の地上・海上気温は深層水形成(および深層海洋大循環)が存在しない場合に比べて高い状態が実現されます。形成された冷たい深層水は中低緯度で湧昇し、海面に対して下から冷却を与えることになります。これらの領域での海面水温が深層水よりも十分に高い温度に保たれているということは、海面において上からの加熱があることを意味し、海洋が熱を獲得していることを意味します。同時に大気は熱を失っていることになり、中低緯度の地上・海上気温を低くするように働きます。このように高緯度海洋は熱を失い、中低緯度海洋は熱を獲得し、そしてその間をつなぐように深層海洋大循環は高緯度方向に熱を輸送しており、それが地上・海上気温を決めるのに重要な要素として働いています。
深層海洋大循環が気候において果たす役割は様々ですが、人の生活環境としての気候との関わりという意味から最も重要となるのは、ここに述べたように深層海洋大循環に伴う水平方向の熱輸送とそれに対応した大気−海洋間熱交換であり、言葉を変えるならば気候システムの熱収支における働きであると言えます。海洋と同様に大気も高緯度方向に熱を輸送しており、これらがあわせて太陽光入射量の大きい低緯度と入射量の小さい高緯度の間の温度差を緩和しています(図3)。大雑把に言って、大気と海洋は高緯度方向に同じ程度の熱を輸送しており、温度差の緩和にはどちらもが同じ程度の寄与を持っています。仮に海洋による熱輸送が存在しない状況を考えてみると、その場合には大気による熱輸送がかなり強まると考えられますが、それが海洋の分をすべて埋め合わせることはできず、地上気温の南北差は現実よりもずっと大きなものになるはずです。
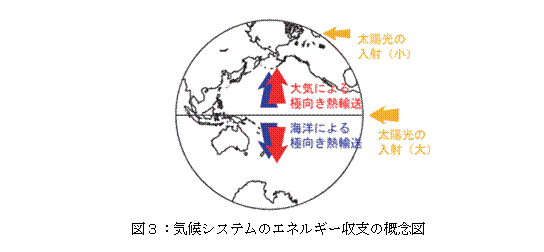
仮想的な場合に限らず、深層海洋大循環の全部または一部が顕著に弱まり、それに伴う熱輸送が顕著に小さくなることは十分に起こり得ます。現実の熱塩循環は、海面における温度に対する外力だけでなく、塩分に対する外力によってもコントロールされます。したがって、たとえ太陽光入射が緯度方向に温度差を作るように働いていても、海面での淡水交換の状況によっては熱塩循環ができない、すなわち海洋が高緯度方向に熱を輸送できないということもあり得ます。実際過去には、最終氷期の終焉期において、北米大陸上の氷床が融解したことによる大量の淡水が北大西洋高緯度域に流れ込み、ラブラドル海ないしグリーンランド海における深層水形成を止めてしまったため、北大西洋高緯度域において温暖な気候状態への遷移が一時的に逆戻りしてしまったと考えられています。また、現在進行中と考えられる地球温暖化においても、それに伴う降水量の変化のためにラブラドル海やグリーンランド海での深層水形成が著しく弱まり、北米からヨーロッパにかけての温暖化の進行に大きな影響を及ぼすかもしれないと考えられています。これらの例からもわかるとおり、海洋深層大循環とそれに伴う熱輸送は、海面での淡水交換によって大きくコントロールされるという一面があります。気候、とくに人の生活環境としての気候に対する海洋深層大循環の影響としては熱輸送の働きが大切なわけですが、海面での淡水交換と海洋による熱輸送がどのような関係にあるのかを明らかにするというのが海洋深層大循環と気候との関わりを考える上でのひとつの重要な鍵であると言うことができます。
気候システムの水循環という観点から
気候の中で水は特別な重要性を持っています。前に述べた大気・海洋・雪氷・陸面といった気候システムの各要素のいずれにおいても水は存在し、各要素間での交換が存在します。また、地球の気候状態において水は固体・液体・気体の三態すべてが有意な量だけ存在し、水の交換・輸送と相変化が気候システムにおけるエネルギー循環の大きな部分を担っています。したがって、気候システムの中を水がどのように巡っているのかは、気候を理解するうえでひとつの重要な視点となります。言うまでもなく海洋は気候システムにおける水のほとんどを保持しています。そうした水の貯蔵庫あるいは供給源としての役割を果たすのみならず、海面における淡水の出入りが熱塩循環の駆動原因となるため、気候システムの水循環は海洋深層大循環と密接に関連し、ひいては海洋による熱輸送、そして人の生活環境としての気候においても重要な意味を持っています。
熱塩循環の熱的側面と塩分的側面は物理的に(より数理物理学的な言葉を使うならば、力学系としての性質が)大きく異なります。これは、熱塩循環の熱的な駆動要因である海面での熱交換が海面水温に依存するのに対し、塩分的な駆動要因である海面での淡水交換が海面塩分に直接は依存しないという違いによります。熱塩循環の変化による海洋熱輸送の変化は海面水温の変化を通して海面熱交換を変化させるのに対し、海洋塩分輸送の変化に伴う海面塩分の変化は海面での淡水交換である降水量や蒸発量を直接変化させはしないのです。このため、海面熱交換に変化が生じた場合にはそれに対する熱塩循環の応答の結果は原因となる変化を打ち消す方向に働く(負のフィードバックを持つ)のに対し、海面淡水交換に変化が生じた場合にはそのような働きがありません。したがって、深層海洋大循環は気候システムの水循環のわずかな変化に対しても敏感に応答し、その結果としての熱輸送の変化を通して、気候システム全体の状態に多大な影響を及ぼし得ます。特に、前に述べたような海洋深層大循環の劇的な変化は、この熱塩循環の塩分的側面の特性によって起こる可能性があるものと考えられています。先ほど述べた最終氷期の終焉期における現象は、そのような特性のひとつの表れと言えます。
気候システムの水循環という観点から見た場合、深層海洋大循環は降水・蒸発・河川流出・海氷・海洋自身の淡水輸送という多くの要素の微妙なバランスの上に成り立っており、さらにその背景には大気の循環に伴う水蒸気輸送や陸上植生の作用を含めた陸面過程の働きが存在します(図4)。これらの要素は直接・間接に非線型的相互作用をしており、その働きが現実の気候においてどのような意味を持っているのかは十分な理解からは程遠い状況です。先ほど地球温暖化に伴う降水量の変化は深層海洋大循環を著しく弱めるかもしれないと述べましたが、実はこれも確実なことではなく、弱まらないという考えにも根拠があるのです。過去に起こった、そして将来起こるかもしれない大規模な気候変動に関して理解しあるいは予測するためには、気候システムの水循環という観点から深層海洋大循環の振舞いを考えることが不可欠です。
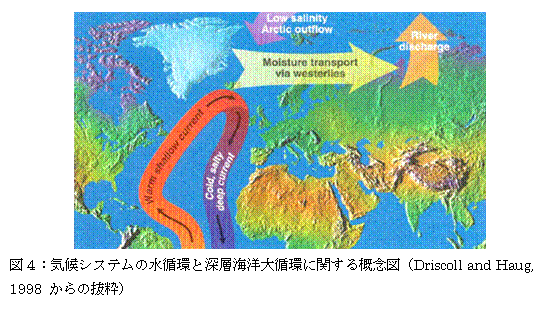
気候システムの物質循環という観点から
地球の気候の歴史を見ると、中生代のような現在に比べて顕著に温暖な気候、あるいは氷期のように現在と比べて顕著に寒冷な気候といった、現在とは大きく異なる気候状態が実現されていた時期があると考えられています。そうした現在とは大きく異なる気候状態の根源的な原因にあるものは大気組成、より具体的には大気中二酸化炭素濃度の違いにあると考えられています。いま問題となっている地球温暖化も、人為起源の二酸化炭素排出の結果となるものです。この大気中二酸化炭素濃度をコントロールするという意味でも、深層海洋大循環は重要な役割をしています。そしてその役割の中では、深層海洋大循環に伴う海洋溶存物質の輸送と海洋中の化学および生物過程の働きが大切な要素となります。
海洋中には溶存二酸化炭素・炭酸イオン・溶存有機物・粒子状有機物・生物といった様々な形で炭素が存在し、その総量は気候システムの要素中で最大です。これらは生物活動(光合成・呼吸・捕食・排糞)や化学過程を通して互いに変換されつつ、一部は海底堆積物となり、残りは深層海洋大循環にのって輸送されます。こうして、熱輸送や淡水輸送と同様に、海洋中の炭素循環が形成されています。大気と海洋は海面を通して二酸化炭素を交換しており、大気あるいは海洋表層の二酸化炭素濃度(より正確には二酸化炭素分圧)変化は他方の変化を引き起こします。例えば、何らかの原因で海洋表層の植物プランクトン量が増加した場合、光合成量の増加に伴って海洋表層の二酸化炭素濃度は減少し、その結果として大気中の二酸化炭素を海洋がより吸収するようになって大気中二酸化炭素濃度を減少させます。この何らかの原因としては、水温の変化や栄養塩と呼ばれる溶存物質の供給を考えることができます。また、海水中に溶けることができる二酸化炭素量は水温に依存するので、生物活動の変化を経なくても、気候変動は大気−海洋間の二酸化炭素交換に変化をもたらします。もちろん、深層海洋大循環が変化すれば、それに伴って海洋炭素循環も変化し、その結果は大気中二酸化炭素濃度の変化として現れることになります。気候の歴史に見られる大気中二酸化炭素濃度の大きな(現在の数割から数倍までの)変化とそれに伴う気候状態の変化を考える場合には、火山活動などによる二酸化炭素供給の変化だけではなく、こうした海洋中の生物・化学過程を考えることが必要となります。
海洋深層大循環および気候システムのモデリング
海洋深層大循環やそれとつながる気候システムの研究においては、数値モデリングという手法が今や欠かせません。これは、気候システムにおける様々な過程(力学・熱力学・化学変化・生物活動など)とそれらの間の相互作用を数学的に表現し、それを計算機上で数値的に解くことにより、気候システムの全部または一部の現在・過去の状態をシミュレートしたり、未来の状態を予測するものです。あるいは、ある特定の過程や相互作用の働きを変化させた計算をして、その結果からその過程や相互作用の気候システムにおける重要性を調べるという、実験としての使い方もされます。気候システムは、その単一の要素を取り出してすら、実験を行うことは不可能な系なので、このような「模型」による実験がどうしても必要であり、そして有用なものとなります。
このような数値気候モデルは世界中の複数の研究機関で開発されており、東京大学気候システム研究センターもそのような機関のひとつです。その中でも、大学にあって数値気候モデル開発を行い、それを用いた教育および研究者養成を行っているというのは他に類を見ません。我々の研究グループでは数値海洋モデルを開発し、それを単独で用い、あるいは気候システム研究センターの他の研究グループで開発された他の要素の数値モデルと結合した数値気候モデルとして用い、これまでに述べたような現象や問題の解明にあたっています(図5)。