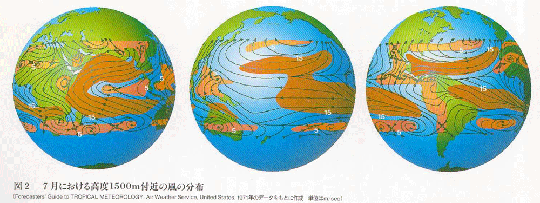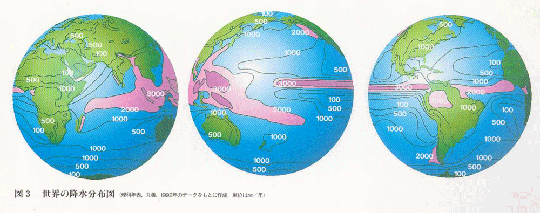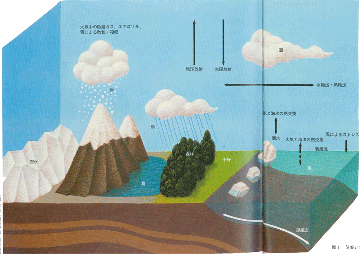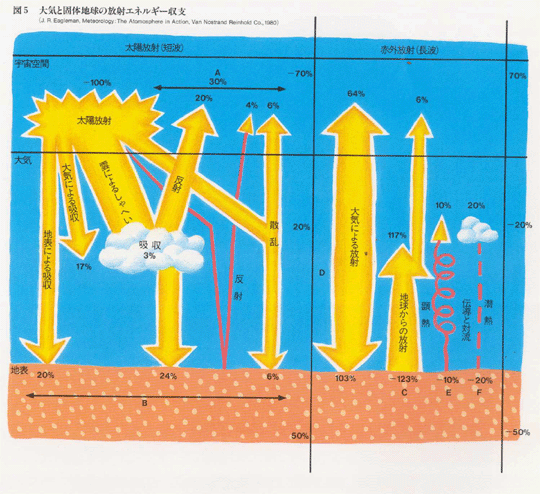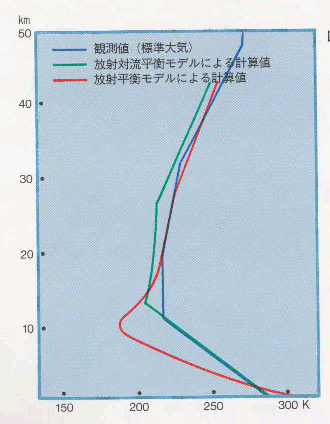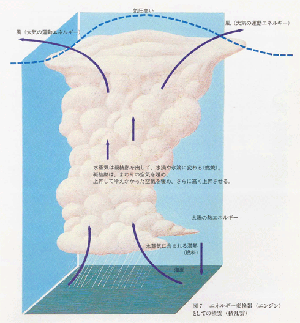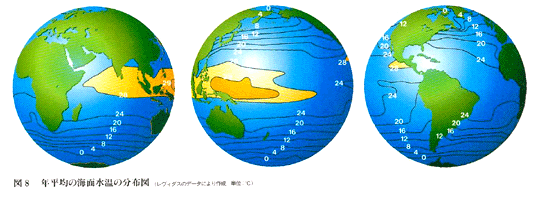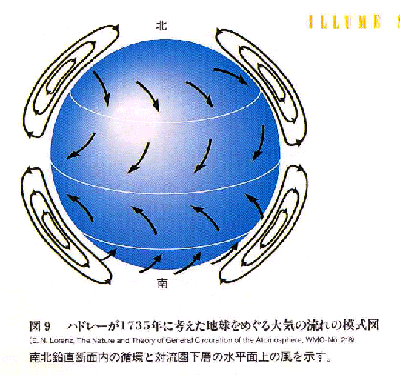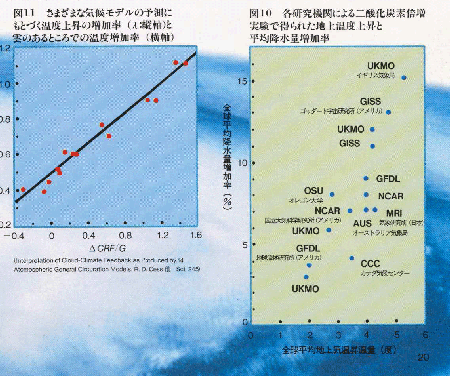雨水が新鮮な飲み水?
つい先日、西太平洋赤道域に存在するパプアニューギニア共和国のマヌス島に行ってきました。マヌス島といっても知らない人が多いことと思いますので、西太平洋の熱帯域の地図を出しておきます(図1)。東京からはるか南、赤道のすぐ南、南緯二度にある小さい島です(注1)。
 | |
| 図1マヌス島(パプアニューギニア) |
(注1)そこには、北海道大学理学部・低温科学研究所の研究者を中心にした観測隊が、熱帯での降水システムを観測するために滞在していました(写真)。彼らは、1992年11月から1993年2月にかけて、国際的な協力のもとに行なわれているTOGA-COARE(トガーコア)と呼ばれている国際共同観測に、日本を代表して参加しているのでした。この観測は、地球の気候システムの重要なサブシステムである大気と海洋の相互作用を研究するためのものでした。
(注2、3)赤道地域の面積は、赤道の長さ40000km、南北10度の距離を2000kmとして、8×107km21.
日4mmの降水で、その地域に降る年間の雨の量は、4×10-3m x365×8×107×106 m2 =116.8×1012m3となる。水1m は1トンの重さだから、赤道域に降る雨の年間総量は116.8兆トン。蒸発に必要な熱量は、116.8×l012×106gx594cal/g=6.94×1O22cal。1kWh=860×103calで換算して、必要電力量は6.94÷860×1022×10-3kWh=8.07×1016kWhになる。 |
マヌス島のホテルには冷蔵庫があり、そのなかに飲料水が入っていました。そしてその容器には、「fresh rainfall-water(新鮮な雨水)」と書いてありました。
現代文明にどっぷりとつかっている都市に住んでいると(最近でこそおいしい水のブームですが)水道の水こそが飲み水であると思いがちです。少なくとも雨水などは、飲むに催しない汚れた水、と感じています。しかしよく考えてみると、雨というものは空気中の水蒸気が凝結したものですし、降水プロセスというものは、地上なり海洋から蒸発させた水蒸気を凝結させる「真水の製造プラント」と考えることができます。
もちろん、雨というのは厳密に考えれば、純水ではなく、たとえば二酸化炭素などが若干とけ込んでいます。しかし、このような成分は汚染物質ではありません。雨が汚れているという印象は、大気中に汚染物質などが浮いており、それが混入してくるからです(そのよい例が酸性雨です)。
日本人にとっては、新鮮な水というと、山のわき水やきれいな川の水を想像します。しかし、これらの水の大本は雨水であり、それが、地面によって濾過されたものなのです。ですから、本来大気の環境がきれいであれば、マヌス島のように、「新鮮な雨水がもっともきれいな水」ということになります。
さて、このような自然の「真水製造プラント」が存在しないと仮定しましょう。しかし、水は人間の生活に、そして動植物の生存に欠かせないものです。そこで自然の「真水製造プラント」の代わりに、人工の「真水製造プラント」で水を製造したと仮定します。
現在の全地球的降水量の分布の正確な値は、まだわかっていませんが、大ざっばに考えて、北緯一〇度から南緯一〇度の赤道域に一日当たり平均四ミリメートルの降水があると考えます。そうすると、赤道域全体では、雨の総量は年間約一二〇兆トン(注2)ということになります。これだけの雨が降るためには、少なくとも同じ量の水を地球表面から(熱帯では、主として海からですが)蒸発させなければなりません。水を一グラム蒸発させるのに必要な熱量を五九四カロリーとすれば、一二〇兆トン蒸発させるのに要する熱量は、約7×1022 cal.、これを電気で賄うとすると、8×1016KWh(注3)ということになります。
平成二年度の日本の総発電量は、約八五七〇億KWh(8.57×1011KWh)でした。つまり、この赤道地域の全降水量を電気によって賄おうとすると、日本の総発電量の一〇万年分程度の電力が必要ということになります。
つまり、自然はこれだけのことを無料で行なってくれているのです。もつとも無料ですから、いつも同じょうにというわけにはいきません。ですから、豪雨と干ばつという自然のきまぐれに人間は泣かされてきたわけです。
現在、東京都の水道料金は、普通の家庭で一立方メートル当たり一一五円です。これは水を作るためのコストではなく、単に水を集めて消毒をするコストが主なので、これだけ安くなっているのです。「水と安全はタダ」と思っている日本人ですが、年間を通して降ってる雨に感謝せずにはいられません。
アジアをおおうモンスーン
さて、水や雨ということになると、日本人であるわれわれの心に浮かぶのは、梅雨とか台風というものです。台風は、いわば嵐がやってくるものという感じであるのに対し、梅雨は雨季という感じがします。この雨季というものは、何も日本だけの特徴ではありません。むしろ、雨季は、熱帯地方に顕著にみられます。
このような熱帯の雨季に関連して良く知られているのが、〝モンスーン″、あるいはもう少し広くして〝アジア・モンスーン″という言葉です。また、このアジア地域を呼ぶときに、多少の誇りを込めて〝モンスーン・アジア″と言ったりします。特に夏のモンスーンという言葉を聞くと、降り続く豪雨のイメージを思い浮かべます。また、私のように団塊の世代より年をとった人たちは、モンスーンというと降り続く梅雨のイメージと、田植えが終わり一面に青い稲がうわっている田圃を思い出します。しかし、このアジア・モンスーンというのは、東南アジアだけに限られた気象現象ではありません。
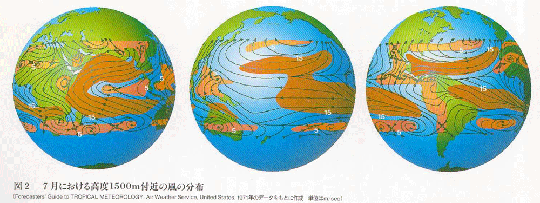 |
| 図2 7月における高度1500m付近の風の分布 |
| (注4)
1500mの高さとは、地球の表面の摩擦の影響がなくなった高さという意味です。ですから、地球規模の大きなスケールの大気の流れが現れてきます。また、水蒸気は大気の下の方ほど多く含まれているので、このあたりの洗れが重要になってきます。 |
地上一五〇〇メートル程度の高さに吹く(注4)北半球の夏の期間の平均の風の分布を見てみましょう(図2)。いわゆる「モンスーンの西風」と呼ばれる風系が、南半球のインド洋からアフリカ大陸のソマリア沖で北上して北半球にはいり、アラビア海を吹き渡り、インド、インドシナ半島、そして、中国南部、さらに、日本にまで、一万キロメートルにもおよぶ広がりをもつていることに気がつきます。
モンスーンという現象は、アジアの人びとの生活に深く密着しており、それぞれ地域的な名前をつけて呼ばれています(インド・モンスーンやインドシナのモンスーン、中国のモンスーン、日本のモンスーンというように)。特にインドでは、モンスーンの観測が昔からあり、インド人は古くから研究をしていたので、モンスーンといえば「インドが本場である」と主張しがちです。しかし、アジア・モンスーンというのは、インドというような一地域の現象ではなく、ユーラシア大陸程度の大きな水平スケールをもつ気象現象である、ということができると思います。
膨大なエネルギーを放出する雨
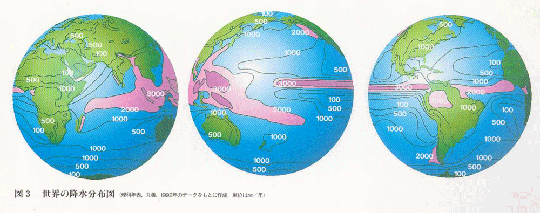 |
図3 世界の降水分布図
(理科年表、丸善、1992年のデータを元に作成、田にはmm/年) |
|
(注5)熱束収束帯 (Inter Toropical Convergence Zone) 熱帯域(北緯7度~10度、南緯7度~10度あたり)にある対流活動が盛んな地域のこと。
|
モンスーンといえば雨です。ですから次に雨について見てみましょう。図3は理科年表をもとに作成した年間降水量の図です。特に熱帯域の降水量の分布に注目してください。
先ほど、東西に平均すれば、熱帯域では年間一日当たり四ミリメートルの雨が降っているといいましたが、降水量は場所によって非常に異なっていることに気がつきます。とりわけインドからインドシナ、あるいはインドネシアや中国南部、そして西太平洋地域(これらを総称して、〝モンスーン・アジア″と呼んでいるのです)の降水量がとびぬけて多いことに気がつきます。
これらの地域の豊かな降水は、稲作を可能にしています。稲作、あるいは水田耕作は、土壌の荒廃を招かず、単位面積あたり最大の人口を養うことを可能にします。豊穣なアジアというわれわれの持っているイメージは、溢れんばかりの降水と、豊かな農作物によっています。またアジアの人口密度の高さも、勤勉さをもたらす文化も、この水田耕作に基礎をおいていると考えられます。
これに匹敵する降水量は、太平洋東部の熱帯収束帯(注5)(北緯七度あたり、西経九〇度から日付変更線のあたりまで)に対応する東西に延びた線上の部分と、アフリカやアマゾンの熱帯酪林帯、および大西洋の熱帯収束帯のところに見られます。しかし量的に比べてみれば、モンスーン・アジアの降水量は世界最大ということができます。先ほど、「水を蒸発させて雨を作るには、エネルギーがかかっているのだ」と書きました。同じように、水蒸気が凝結するときには、水を蒸発させるときに要した熱量と同じ熱量が放出されます。
つまり、モンスーン・アジア城には、この地域の降水量に見合う、膨大なエネルギーが放出されていることにもなるのです。上層を流れている偏西風やジェット気流などの大規模な大気の流れは、このエネルギーによって維持されているのです。このことは、この地域の雨の降り方が世界の気象に大きな影響を及ぼしていることを示唆しています。
モンスーンはどうして起きる?
前の節で、ユーラシア大陸の南縁に沿って一万キロにもおよぶ西風が吹いているといいました。「モンスーンは、陸地と海の熱容量の差によって起きる、いわば海陸風のようなものである」ということは中学校で勉強するはずです。しかし、アジア・モンスーンでいうところの陸というのは、実はユーラシア大陸というような大きな大陸のことなのです。同じように海というのは、インド洋から太平洋におよぶ地球スケールの海なのです。ですから、自転する地球上で起きる地球の回転の影響を受けた「大きな海陸風」と考えることができます。
しかし、地球スケールの海陸のコントラストが、アジア・モンスーンを引き起こしているということを考えると、モンスーンを単に「地球の回転の影響を受けた大きな海陸風」というイメージだけでとらえてよいのだろうか?
という疑問がわいてきます。
たとえば、大陸の陸面の温度について考えてみましょう。大陸の陸面の温度といったところで、それは一つの値ではありません。大陸の地表面の状態ほど多様なものはありません。熱帯雨林帯もあれば砂漠もあります。ですから、単純に大陸といって温度を一つの値で代表させることには問題があります。
問題はそれだけではありません。陸の温度は夏と冬では大きく異なり、一年を通して変動していきます。この温度変動は、毎年まったく同じ変動を繰り返すのではなく、年ごとに前年とは違った変動をします。たとえば、ユーラシア大陸には冬には雪が降り、夏には溶けます。しかし冬に大量の雪が降れば、夏になって溶けるのに時間がかかると考えられます。そうするとその年の陸面の温度は、それほど上がらなくなるということになります。一方、土壌というのは熱容量が小さいので、短い時間で急速に熱くなるという考え方もあります。ですから、前の冬に降った雪の量にはあまり依存しないということになります。そうすると、地面温度はむしろ日照時間に左右され、雲の出方など大気の気象条件に大きく依存するということになります。
同じように、海の海面水温も一様ではありません。海面水温も場所ごとに異なりますし、年ごとに変動しています。たとえば、エル・ニーニョと呼ばれる現象があります。エル・ニーニョになると中部太平洋の海面温度が高くなります。そうすると、その付近の積雲活動が活発になり、多くの雲が立つことになります。
積雲活動にはおもしろい性質があり、ある場所で積雲の活動が活発になると、積乱雲上部から流れ出る空気の流れは、積雲群の周囲では下降気流となり、その付近での積雲活動が抑制されます。この働きによって、熱帯雨林帯の付近には砂漠が存在するのです。ですから、エル・ニーニョによって太平洋中央部の積雲活動が活発になれば、(どちらが原因でどちらが結果かわかりませんが)その西側のモンスーン・アジア地帯での積雲活動が抑制され、モンスーンの活動が弱くなることになります。
難しい降雨量の測定
降水量の分布を見て、「モンスーン・アシアが多い」などと述べましたが、定性的には正しいにせよ定量的にどの程度正しいかについては問題かあります。陸上や島の上の降水量は、とにもかくにも雨量計がありますので、信用てきるだろうと思うかも知れませんか、「雨を計る」ということはそれはと簡単なことではありません。特にある地域に降った雨の総量や、あるいはある地域の平均の降水量といった量を計ることはなかなか大変なことてす。なせかというと、雨の降り方というものは場所によって異なりますし、また局地的な地形や、建物の影響を強く受けます。ですから雨量計に入った水は、雨の量としては正しいとしても、それがその周辺地域の平均の雨量を表現しているかということについては、慎重に検討する必要かあります。
陸上でもこれたけ大変てすから、海上の降水量の測定についてはもっと大変てす。海の上では、雨量計を胎やブイの上に置いて計ります。しかし、雨が降っているときには、おおよそ海は荒れています。波は高くしぶきがかかってきます。このような中では、雨だけを正確に区別して′則定することは不可能です。
このように雨を計るということは大変なことなのてす。しかしなから現在では、全地球上の降水量を定量的に測定することか気候の研究にとって非常に重要であると考えられています。「こんな量もまた計られていなかったのか?」とひつくりされるかも知れませんか、全地球的に測定するということは大変なことなのです。そのため最近では、人工衛星に降雨レーダーを搭載して、地球上の雨の量を正しく測定しようという試みが行なわれています。
|
気候システムのメカニズムは?
このことは、陸地と海洋との熱的な性質の差で、太陽に照らされたときの温度が異なってくるようになり、それにともなって風が吹く、というような単純な理解だけでは、アジア・モンスーンの本質が理解できないということになるかと思います。
たしかに、モンスーンは海陸の熱的コントラストによって引き起こされます。しかし、この熱的コントラストができる段階で、さまざまな要因が働きます。さきに述べた冬の潮間の降雪量もその一例です。そのほか海の状態、陸地の湿りぐあい、大気の状態、風の吹き方など、あらゆることが原因となり、また、それらのことが結果となるなどして海陸のコントラストが決められていきます。
つまり、アジア・モンスーンについて考えるときには、この地球上の気候を形成しているもろもろの要因すべてに気を配らなければならない、ということを意味しています。
この地球上の気候は、気候システムという一つのシステムとして、形成されていると考えられます。ここでシステムという言葉を使うのは、気候というのがさまざまな性質の異なるサブシステム
(たとえば、大気や、海洋や、雪や氷、地表面の状態など)から成り立っていることだけによるのではありません。実はそれぞれのサブシステムが、互いに相互作用を行なっており、全体としての系がなんらかの変動を余儀なくされたときに、それぞれのサブシステム間でいろいろな相互作用を行ない(フィードバック)、システム全体として一定の方向に反応するような性質を持っているからです(図4)。
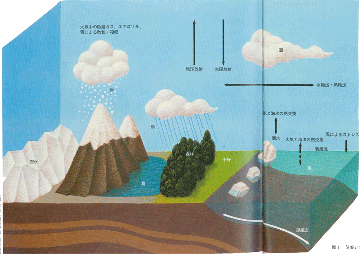 |
| 図4 気候システムの概念図 |
それはちょうど人間の体が、目や耳、手や足、腕や心臓などさまざまな部品から成り立っていながら、単に脳だけの命令で働く中央集権的な機械的なシステムではなく、それぞれが単独に存在するのでもなく、全体として有機的に働くシステムであるようなものです。ですから、それぞれのサブシステムの特徴に気を配りつつ、気候システム全体の特性を考えていくことが必要とされています。しかし、現状は、気候システム全体をシステムとして維持しているメカニズムが何なのか、まだ、ほとんど何もわかっていないという状況です。今後の研究が必要とされる由縁です。
二つのキーワード〝エネルギー″と〝水″
前の節で、気候システムは全体として考えていかなければならないといいました。では、具体的にはどうすればよいのでしょうか?
気候システムは、さまざまなサブシステムの間の相互作用のシステムです。ですから、全体を理解するということは、この相互作用がどのように行なわれているかということを理解することにほかなりません。相互作用がわかれば、残っているのはそのサブシステムの中での独自の運動ということになるからです。こうした研究は、いままで気象学や海洋学などの、それぞれの分野で行なわれてきた研究にほかなりません。
サブシステム間の相互作用を考えるときに重要なことは、その相互作用によって何が伝えられるかについて注目することです。
まず最初に、気候システムを「物理的なシステム」と考えてみることにしましょう。
物理的なシステムを特徴づけるには、エネルギーを考えるのが妥当です。エネルギー、あるいはエネルギー保存則は、大気現象を物理的に考えるときの基本的な考え方です。物理的な原理は、基本的には「無から有は生じない」という保存則が基になっています。物事を動かし続けていくにはエネルギーが絶対に必要である。あるいは、ある現象があれば、必ずそれをもたらす原因があり、それにはエネルギーが重要な役割を担っているということです。
したがって、気候システムを考える時のキーワードは、まずエネルギーということになります。地球に入ってきた太陽エネルギーが、どのようにして各サブシステムの間を流れていって、最終的に宇宙に出ていくのか、このエネルギーの流れを理解することです。
もう一つキーワードをあげろといわれたら、それは水です。言うまでもなく地球は水惑星として、太陽系のなかで出色の惑星です。われわれの日々の生活に影響を与える毎日の天気の変化も、気候の多様性も、みんな水の変化に依存しているのです。ですから、気候システム中での水の動きを理解することが次の柱になります。
温度と降水量という二つの測定値が、気候学で気候区分をするときの基準として良く使われています。このことは、先ほど述べたエネルギー(温度)と、水循環(降水量)によく対応します。ですから、気候システムを「エネルギーと水の循環を軸に理解する」ということが、気候を理解することにほかならないのです。
冒頭で熱帯の西太平洋で大気と海洋の相互作用の観測を行なっているトガーコアと呼ばれている国際共同観測をご紹介しました。気候システムを、エネルギーと水の循環しているシステムと考えると、その核心的な部分は熱帯、特に暖かい海の上で、活発な積雲対流のあるところ、つまり雲がわきたっているところということになります。
この地域の大気と海洋の相互作用を理解するということは、気候システムのエネルギー源を理解することにもなるのです。
太陽エネルギーの流れ
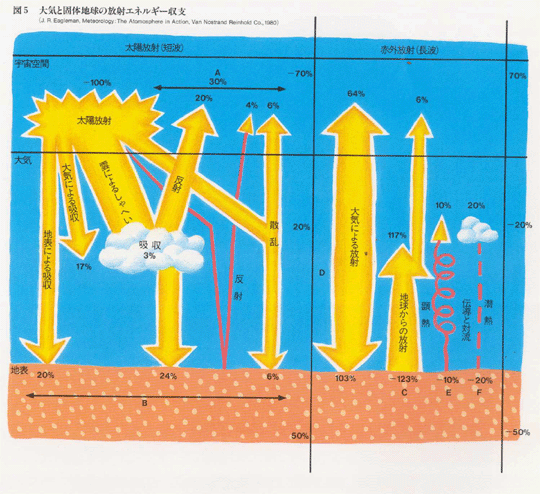 |
図5 大気と固体地球の放射エネルギー収支
(J. R. Eagleman, Meteorology:The Atomosphere in Action,Van Nostrand, Reinhold Co. 1980) |
先に、エネルギー保存則ということが重要であるといいました。そこで、ここでは、われわれが目にする雲や雨や風などの大気現象のエネルギー源について考えることにしてみましょう。
言うまでもないことですが、大気現象のエネルギー源は太陽です。太陽のエネルギーが、地球表面上の森羅万象の大本です。
太陽エネルギーは、次から次へと流れ込んできます。放っておいたら、地球はどんどん熱くなってゆくはずです。しかし、現実には一年を平均して考えると、毎年ほとんど温度は変わっていません。(それでは、最近問題になっている地球温暖化とは何か、ということを質問する読者の人は多いことと思いますが、温暖化の度合いはきわめて小さいものです。このことが温暖化の予測をむずかしいものにしています。)
平均して考えれば変化がないということは、入ってくるエネルギーと出ていくエネルギーが等しい、ということを意味します。このような時、システム平衡であるといいます。図5は、太陽からのエネルギーがどのようにして入ってきて、どのように出ていくかを示したものす。太陽からのエネルギーは、雲や地表によって、三〇%程度が反射されますが(図5中のA) その残りは一部分が大気に吸収され、大部分が地表に到達します。
われわれは、深い「大気の海の底」に住んでいます。それにもかかわらず、まわりが明るい、あるいは植物が太陽の光を利用して光合成ができるのは、この大気の性質によっているのです。比較のために、海の底を考えてみてください。水は太陽の光をよく吸収します。光の大部分は海面から一〇〇メートル以内で吸収されてしまいます。ですから、深い海の底は暗黒の世界となります。生物が進化し、彩りに満ちた地球が実現されたのも、太陽の光が大気を通って地表にまで降りてきているからです。
地表に届いた太陽のエネルギーは、地表で吸収されます(図5中のB)。そして、今度は逆に、大気に向かって放出されます。この地表面から大気に向かう熱エネルギーは、いろいろな形をとって運ばれます。その一つは地
球による放射です(図5中のC)。この放射は、「地球放射」あるいは、太陽の放射と比べて波長が長いことから「長波放射」と呼ばれています。
地球の表面をおおう大気も長波放射を出しています(図5中のD)。この放射は、地表にも降り注いでいます。この注ぎ方が多くなるのが、いわゆる温室効果(この効果をもつ気体の増加にともない地球の温暖化をもたらす)と呼ばれるものです。ですから、地表のエネルギーを逃す効果をもつのは、この地球放射の正味の差ということになります。そのほかのエネルギーの移動の形には、顕熱輸送(直接大気を暖めること)(図5中のE)、あるいは、潜熱輸送(蒸発による熱輸送)(図5中のF)があります。このなかでは、蒸発による潜熱輸送が大きな役割をしめています。
大気の放射と対流によるエネルギー平衡
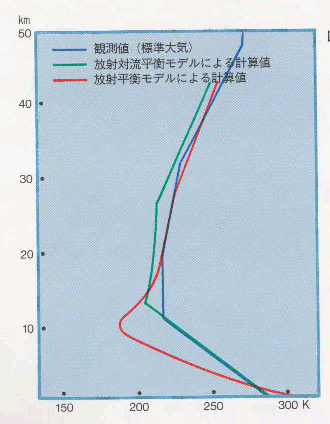 |
図6 放射・対流平行モデルによって計算された大気の温度分布と観測値
(S. Manabe and J. Atomos. Sci 21,1964) |
放射過程だけを考えて作られる大気の温度構造をみてみると、大気の状態は重力的に不安定、つまり冷たく重い空気が上に、暖かく軽い空気が下に存在することになります。暖められた地表の空気は、浮力によって上層に昇っていきます。すると、上の方は下に比べて気圧が低くなっていますから、空気はそこで膨張することになります。このとき、膨張した空気は周りの空気を押し出すという「仕事」をします。この「仕事」によって、地表から空気に与えられた熟エネルギーは、上の方の大気に伝えられます。
つまり、このような大気の対流現象によって、太陽から地表に与えられた熱エネルギーは、大気の上層に伝えられます。このとき水蒸気の凝結があれば、さらに、凝結熱が出ますので、空気はもっと高く昇り、もっと大きく周りの大気をかき回すことになります。
このように、大気放射と対流によって大気のエネルギー平衡が成り立っている、と考えることができます。そこで、このようなモデルを、「放射・対流平衡モデル」と呼んでいます。このようなモデルで計算した大気の鉛直の温度構造を図6に示しました。現実の大気の構造をよく再現できていると思います。ただし、地表から一〇キロメートル程度の温度の傾きは、理論が予測したものではなく、経験的な事実を入れたものです。この傾きをも自動的に計算するためには、さらに複雑な「大気大循環モデル」を用いなければなりません。
積乱雲は大気を動かす”エンジン”
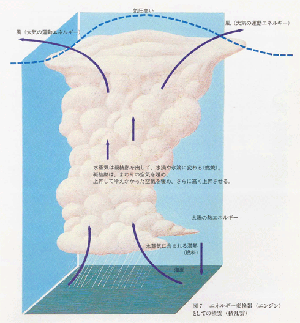 |
| 図7 エネルギー変換器(エンジン)としての積雲(積乱雲) |
地表から大気に加えられた熱エネルギーは、対流のなかで空気の塊を上昇させるのに使われます。上昇した空気は、途中で断熱膨張で冷えながら、ある高度に到達し、周りの空気を押し出します。このような対流は、熱帯では、水蒸気の凝結をともなった積雲対流(具体的には雲、特に積乱雲)という形をとります。このようなときに、雲の中で、主として放出されるエネルギーは、水蒸気の凝結にともなう凝結熱です。言い換えると、熱帯地域にある雲、特に積乱雲は、「大気の下層で水蒸気という〝燃料″をもらい、雲の中で燃やして、大気を動かすというエネルギー変換器」と考えることができます(図7)。
この「変換器」としての票の特徴のひとつは、外部の条件に非常に左右されることです。たとえば暖かい海面水温の海では、一般的によく害が立ちます。これは大気全体が下から暖められて、雲が立ちやすくなっているからです。また、低気圧や台風などにともなう大気の流れによっても雲が立ちます。これも大きなスケールの流れが、雲が立ちやすい条件を作っているからです。
しかし、雲が立つか立たないかはこのような地表の条件、あるいは、大気の大規模な流れによってすべて決まっているわけではありません。そもそも大気の大規模な流れは、このような積乱雲にともなう熱エネルギーによって維持されているのですから、雲が立つことが大気の流れを変えてしまうということも可能なのです。大気の流れが変わると、いままでは雲が立っていなかったところに雲が発生することも可能となります。
地表に加えられたエネルギーを汲み出すボンプの役割を果たす積乱雲が、地表の条件だけで発生するのではなく、逆に、自分で勝手に動いていくこともあるという、具体的な一例は台風です。台風は、自分のなかに存在する雲のなかで発生する凝結熱をエネルギー源としています。
台風の動きを見ていると、規則正しく上層の大気の流れに乗ってくる場合もあれば、「迷走台風」と呼ばれるような好き勝手に動き回る場合もあります。この場合は、雲の集団(つまり台風)がその周りの大気の流れを変化させ、好きなところに動いていくと考えることができます。こうしたことが、気候の振舞いに多様な彩りを与えています。
一年周期の変動
前にも述べたように、地球の気候は太陽によって基本的に決定されています。一方、地球の自転軸は公転面に対して垂直ではなく傾いています。したがって、地球上のある地点に注ぎこむ太陽のエネルギーは、一年を周期として変動しています(もちろん、一年以外に半年の周期も存在します)。この二つの事実を合わせて考えると、気候とは、それぞれの地域、土地で繰り返される〝年変化-季節変化″のパターンのことであるといえます。一年を周期として変動する太陽放射を外力とし、それに強制されながら変動し、かつ自らのシステム内部に存在するメカニズムにょっても変動していることが気候の本質といえます。
このように、気候とは基本的に一年を基礎とする年変化から成り立っています。しかし年変化とはいいながら、毎年毎年同じ季節変化を繰り返しているわけではありません。
大気の流れは本質的に乱れています。ですからなにも理由がなくとも毎年毎年同じにはなりません。したがって、変化による違いに意味があり、その道いの原因を考える必要があるか否かを考えるためには、その差が大きいか小さいかを判断する基準が必要になります。数十度程度の変動を基準にすれば、「夏になると暑くなり、冬になると寒くなる」という程度の気温の年変化に関しては、地球上のほとんどの中・高緯度では毎年「同じ」ということになります。一方、熱帯域では、温度に関する年変化はもともと小さいので、季節変化は乾期と雨期で特徴づけられます。この乾期・雨期のサイクルも毎年同じになるわけではありません。
このような一年を基礎とする年変化・季節変化にとつて重要になるのが、「海陸コントラスト」です。なぜかというと、太陽による入射量の年変化によって、地表面温度は大きく変化します。一方、海面水温の方は、その大きな熱容量のゆえに、それほど大きく変化しません。特に熱帯域では、その変化は微小です。ですから、海洋と大陸の熟的コントラストは、大きな季節変化をもたらすことになります。
季節変化そのもののモンスーン
モンスーンとは、もともとは季節にともなって風の流れの方向が反転すること、そしてその季節の中では、風向きがほぼ一定していることを意味しています。このことは、モンスーンが海陸の熱的なコントラストにともなって引き起こされる大気の流れのことであると考えると自然に理解できます。
季節変化にともなう海陸の熱的コントラストは長続きします。ですから、大気の流れがこの熱的コントラストによっているのならば、引き起こされる流れも、季節のなかでは一定で、しかも季節の変化とともに変わることになります。
さらに、このような地表の条件によって大気の流れが引き起こされるためには、エネルギーの変換器である雲、積雲対流がモンスーンにともなって起きなければならないということになります。ですから、モンスーンという言葉は、当初は、季節風のことを意味していましたが、雨のことも意味するようになりました。
しかし、雨を降らせるには、水蒸気が必要です。この水蒸気を運ぶのは空気の流れです。そして、この空気の流れは、雨の降り方によって生じます。
このように、大気の現象は、正確にどれが原因でどれが結果とはっきりわかる例はそれほど多くありません。実際には、ほとんど、同時現象として起きてきます。ですからモンスーンとは、季節の進行にともなう雨と風の変化と考えて良いと思います。
アジアの海にはエネルギーがつまっている
ここで再びアジア・モンスーンを見直してみましょう。図8の年平均の海面水温の図を眺めてみてください。
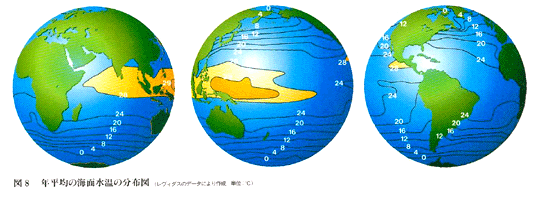 |
図8 年平均の海面水温の分布図
(レヴィダスのデータにより作成 単位: ) |
西太平洋からインド洋にかけて、摂氏二八度以上の暖かい海水温が広がっていることが見てとれます。しかも、注意してほしいことは、このような暖かい海水温は、世界のどこを探してもほとんどないということです。ほんのすこし、メキシコの南側に存在するだけです。ですから、モンスーン・アジアをとりまく海は、世界でもっとも暖かいということを覚えておいてください。
暖かい海では、蒸発によって大気にエネルギーを供給できます。言い換えれば、暖かい海というのは、エネルギーの缶詰みたいなものです。ですから、アジアの周りの海には、エネルギーの缶詰が、ごろごろ転がっているというわけです。
次に、大陸を見てください。太平洋・インド洋と対比をなす形で、広大なユーラシア大陸が広がっています。ですから、アジアをめぐる海陸のコントラストは、他のところと比べものにならないくらい大規模なもの、世界一のものであるということができます。
先ほど、アジア・モンスーンにともなう降水量は世界最大であると述べましたが、その理由は、この世界最大の海陸コントラストと、世界でもっとも暖かい海のせいなのです。
気候のエッセンス「エネルギーの移動と水の循環」
今までのことをまとめて考えると、気候とは何かについておぼろげながらイメージがつかめます。
地球の気候システムは、太陽のエネルギーを源にして動かされています。この気候システムの基本的な振舞いとは、地表面に入った太陽エネルギーが、あちらこちら水平方向に鉛直方向に運ばれていき、最終的に宇宙空間に捨てられるプロセスと考えることができます。
このとき、地表面から大気に運ばれるエネルギーは、直接大気の熟エネルギーとして運ばれるものよりも、水蒸気の形で、蒸発によって大気中に運ばれているもののほうが多いということが重要です。ですから、水平方向や鉛直方向に熱が運ばれるというときに、単に暖かい空気がどこに運ばれるのか、ということ以上に、水蒸気が水平方向に運ばれてどこで凝結するか、ということが大事になります。
つまり、水蒸気がどこで蒸発し、どこに運ばれ、どこで凝結するかという水の流れ、水の循環が非常に重要になります。ですから、気候システムとは何かといえば、それは水とエネルギーの流れ、太陽から入ってきたエネルギーが、水とエネルギーの移動を通して、最終的にどのようにして宇宙に放出されるかということになります。
卓越する束西方向の流れ
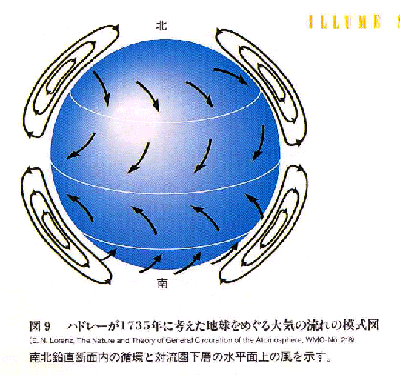
まず、水平方向のエネルギーと水の流れを見てみることにします。地球の大気の流れを見てみると、東西方向に一様で南北方向で違いのある流れと考えることができます(図9)。このように、東西に一様な流れができる理由は、地球が東西方向に回転しているからです。地球が回転しているので、東西一様になるという理由は、数式を使わないで説明するのはなかなか難しいことです。簡単には以下の説明で理解できると思います。宇宙から地球の大気を見ると、地球の自転とともに大気もものすごい速さで西から東に回転していることになります。大気にも慣性ということがありますから、このように東西に走っているときに、その流れからずれて、南北に流れるのはなかなか難しいことになります。
木星など他の惑星の写真を眺めてみれば、東西方向での縞々が目立っているので、回転する球面上の大気の動く方向は東西方向が多いらしいということは納得できることと思います。地球では雲が適当に存在してますので、東西に非一様に見えますが、その雲の動きを見てると、基本的には東西に動いていることがわかります。
モンスーンは束西に非対称な流れを生む
ところが、細かく見てみると、大気の流れはけっして東西一様の流れになっていません。日本付近の流れが、南北に波打っているのは、東西一様の流れの中に、渦が存在していると考えることができます。ですから、このような流れの蛇行は、東西一様の流れからのズレと考えてみることができます。しかし、熱帯地方はそうではありません。
先ほどの概念的な大気大循環(図9)では、熱帯地方は貿易風の東風になっていますが、現実の大気の流れを見てみると(図2)、アラビア半島の南からインド-インドシナ-中国南部-日本に至るまでの、一万キロメートルにおよぶ西風が吹いています。つまり、回転する地球ということでは、東西方向に一様の流れになりますが、その流れを変えて、東西に非対称の流れを作り出しているもの、それがモンスーンであるといえます。
こうしたことが生じるには、東西に大陸と海洋のコントラストがあることが基本的に重要です。大陸の形成は、大陸移動によってできたとされています。現在のプレートの動きを見ていますと、太平洋、大西洋の中央に大きな割れ目が南北に入っています。そして、プレートは、東西に動いています。アフリカ大陸の東側に入っている割れ目(大地溝帯)も南北に伸びています。このような地球内部のマントルの動きにともなって、とにもかくにも現在の大陸配置がなされたところに、モンスーンが引き起こされる理由があるのです。
しかし、東西の海陸コントラストは、何もアジアだけではありません。アメリカ大陸とアフリカ大陸の間には大西洋があります。ユーラシア大陸と太平洋・インド洋との関係と同じく、これも東西の海陸コントラストです。
しかし、アメリカ東海岸に、アジア・モンスーンに相当するモンスーンがあるということは問いたことがありません。アメリカ大陸、およびアフリカ大陸でモンスーンが存在するといわれているのは、北半球の夏の西アフリカ・モンスーン(コートジボアールからガーナのあたり)と、メキシコの南側にできるメキシコ・モンスーンだけです。
東西と南北のコントラスト
この理由を考えてみます。地図を眺めてみますと、この三者とも、大きくみれば東西の海陸コントラストのもとにあることには間違いがありませんが、そのほかに、程度の差こそあれ、南北の海陸コントラストを持っています。東西の海陸コントラストで積雲が大陸上に立ちやすくなりますが、この南北の海陸コントラストはその積雲を強化することに役立ちます。
上のように考えますと、アジア・モンスーンが世界最大の規模を誇っていることに納得がいきます。ユーラシア大陸とインド洋という、何千キロメートルにおよぶ南北の海陸コントラストが、太平洋とユーラシア大陸という、一万キロメートルにおよぶ東西の海陸コントラストの中に埋め込まれています。これだけの大きさを持っていれば、全世界の大気の流れに影響を及ぼさないわけがありません。
しかし、自然現象は、これだけで単純に考えてよい、というものではありません。モンスーンのもうひとつの代表的な例として、オーストラリア・モンスーンがあります。これは南半球の夏(北半球の冬、十二月の末から三月まで)に、オーストラリアの北側、数千キロに渡って、モンスーンの西風が吹く現象です。オーストラリアも一応大陸と呼んでいますが、このモンスーンは、オーストラリア大陸とインド洋の海陸コントラストだけでできているものではありません。モンスーンの西風は、オーストラリアの東西スケールをはるかに凌駕した東西の水平スケールを持っているからです。それでは、先ほどの公式は当てはまらないのでしょうか?
東西方向の海陸の熱的なコントラストというのは、必ずしも海と陸である必要はありません。基本的には、大気は海陸の区別などはできません。単に、温度、摩擦、蒸発量などが違う表面と思っているだけです。重要なことは東西の熟的なコントラストなのです。
その日で、南半球の海を見てみると(図8参照)、西太平洋からインド洋の暖かい海面水温の領域と、その東側の冷たい海水温の領域という大きな熱的な東西のコントラストがあることに気がつきます。この東西のコントラストのなかに、ユーラシア大陸とインド洋の南北の非対称が埋め込まれているのは、夏の場合と同じです。ただ異なるのは、夏の場合は、大陸が熱くなるというコントラストでしたが、この場合は大陸が冷えるというコントラストになるという点です。もちろん、オーストラリアは、小さいとはいえ無視できる大きさではありません。さきに述べた大きな構造のなかに、オーストラリア大陸とその周りの海から作られるモンスーン循環が埋め込まれているのです。
上下方向の流れー雲と海
次に、鉛直方向のエネルギーと水の流れを考えてみましょう。
このことを考えるときに、誰でも気がつくのは雲のことです。多くの人は、雲ができ雨が降ることになんらの疑問をもつていません。しかし、雲があるところと、雲のないところができ、また、雨が降ってくるという現象はそれほど簡単に説明できることではありません。
まず第一に、水蒸気は冷やしたからといって、すぐには水滴になりません。いや、「部屋の中ではすぐ窓が曇るよ」という人がいるかと思いますが、それはガラスのようなものがあるからです。つまり、水蒸気が凝結するには、中心となる核(凝結核)が必要となります。氷の粒や、大気中に浮かんでいる〝ちり″やゴミ(エアロゾル)などが、このような核になり雲のもとになります。このような核がないときには、大気中の水蒸気は、相当程度過冷却の状態で存在しています。
次に、雨となるためには水滴が落ちてこなければなりません。しかし、水蒸気が凝結している雲のなかでは、一般的に上昇気流が存在しています。そうすると、小さな水滴では落ちてこられません。こうした雨を降らせない雲はたくさんあります。ですから、雨となるためには、小さな水滴が集まって大きな水滴になる必要があります。
このように雲のなかのダイナミクスは、非常に複雑です。しかも、それは雲を取り巻く周囲の涜れとも大いに関連しています。そして、このような要のダイナミクスを理解することが、結局大きな気候システムの変動を解明することに不可欠であるということがわかったのが、ごく最近のことなのです。いままでは、雲のダイナミクスが重要なのは理解できるが、何とかそれを適当にしておいて、うまくいかないかと考えていたのです。事実、天気予報などでは、それほど、雲のことを深刻に考えなくてもうまくいきます。しかし、地球温暖化問題のような微妙な問題の時には、いい加減に扱うことはできません。
鉛直方向のエネルギーの流れで、もうひとつ重要なのは海のなかの流れです。海の底の方にも熱が運ばれています。しかし、海の底に熱を運ぶということは、それほど簡単なことではありません。大気の場合は、暖かい空気は自動的に上に動いていきますから、放っておいても勝手に熱を上に運びます。しかし、海の場合、暖まった海水は、そのままにしておけばいつまでたっても上に浮かんでいます。ですから熱を海の底に運ぶには、強制的に熱を海の底に押し込んでいるプロセスが存在しなければなりません。
このような熱を海の底に入れ込むプロセスが、海洋の深層循環、あるいは、海洋大循環といってもよいのです(『イリューム第7号』「自然と生命の二重らせん」二〇ページ参照)。この海のなかにどの程度の速度で熱が運ばれて行くかということは、大気の状態を考える上でも非常に重要なことになります。
複雑なプロセスをふくむ気候モデル
以上の説明で、気候システムとは何なのか、おぼろげながら理解できたことと思います。まとめてみますと、
(1)気候システムとは、太陽エネルギーによって駆動されている
(2)大陸と海洋の熱的コントラストが重要である
(3)このコントラストによって、どのように雲ができ、どのように熱と水蒸気が輸送されるかで気候の基本的な性格が決まる、ということになります。
気候システムは、よく大気や海洋のサブシステムから成り立っているといいます。しかし、これらのサブシステムは、ばらばらに存在しているのではありません。これらのシステムが相互作用しているという特徴を強調して、われわれは〝大気-海洋-大陸の結合系〟と呼んでいます。
気候システムが〝大気-海洋-大陸〟の結合したシステムであることは理解したとして、具体的にどうすれば良いのでしょうか?
気候システムの理解のためには、結局のところ、大気をあらわすモデル、海洋をあらわすモデル、陸地面をあらわすモデルをつくり、それらの相互作用も的確に表現して全体の振舞いを考えていくしか方法はありません。このようなモデルは、さまざまなプロセスを含みます。なんとかして、簡単に計算できないかという努力が払われていますが、簡単に計算すると、どうしても大ざっばな結論になります。地球温暖化問題のように、政治的な問題になり規制というようなことを考える段階になると、このような大ざっばな結論では役に立ちませんので、やはり細かいプロセスまでいれて計算しなければなりません。
気候の予測
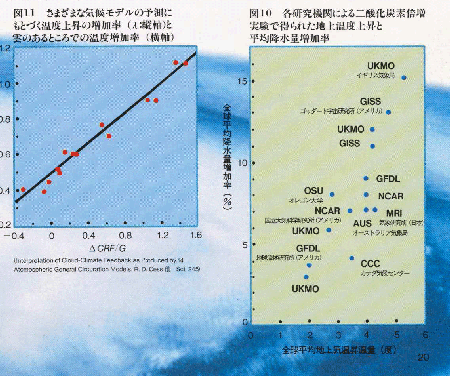 |
| 左側図11 右側図10 |
というわけで、世界の多くの研究機関が地球温暖化の問題に関して「二酸化炭素の大気中の濃度が倍増したときの気温の上昇」を計算しています。その結果が、図10に示してあります。モデルの結果は、ばらついているともいえますし、よくまとまっている、ともいうことができます。しかし、ここで注目してもらいたいことは、このようなモデルの計算結果のばらつきは、ほとんど、それぞれのモデルのなかでの雲の取り扱いの差によるといぅことです(コラム参照)。言い換えれば、モデルのなかの雲の取り扱いについて、もっとわれわれの理解が進めば、このようなばらつきはなくなると考えられます。
地球が温暖化したときの、実際に大事な問題の一つとして、「温暖化したら雨の降り方はどう変わるか、実際どれだけ雨が降るか」というものがあります。水というのは、日本人は「ただ」と思っていますが、生物の存在に欠かせない貴重な資源です。そして、それを人工的に賄うとすると膨大な資金が必要になります。
水循環は、雲などの水平スケールの小さい現象に依存しています。ですから、現在の気候モデルでは、的確な予測を得ることは困難です。このため各モデルによる差は、非常に大きなものになります。
このような地球温暖化にともなう水循環の変化を考えるときでも、基本的には海陸分布にともなう大気の流れがどう変化するか、モンスーンがどのように流れるか、ということを考えるのが非常に重要です。
もう一つ地球の温暖化の問題でわからないことは、海洋の深部にどの程度の速さで熱が逃げていくかということです。この速度が大きければ、当分の間は、温暖化は起きないことになります(ほとんどの熱が、海の中を暖めるのに使われてしまうからです)。現在の議論の要点は二一〇〇年までにどのような変化が起きるか、ということです。ですから、この海の中に、どの程度熱が逃げるかを知ることが、いまわれわれが何をしなければならないか、という点に関連して非常に重要なことになります。
生まれたばかりの「気候システム科学」
われわれ人類が住んでいる地球の表面の環境を形づくっている気候システムの特徴についてお話してきました。それは一言でいえば、〝太陽エネルギーで駆動された水の振舞い″ということができます。空に浮かぶ雲や雨は多様な気象現象の主役です。もうひとりの主役の風も、この〝水の振舞い″と切っても切れない関係にあります。
結局、太陽系第三惑星、水惑星としての地球、ということにつきるかと思います。逆にいえば、この環境こそ人類を生み出した環境ということもできます。このような環境を良く理解して、この環境を悪化させないように努力をしていく必要があります。
地球の気候システムの理解という問題は、最近の「地球温暖化問題」などの具体的な問題に触発されて起きてきました。ですから、参考になる教科書も、理論もあるわけではありません。「気候システム科学」というのは、いわば、生まれたばかりで形も何も決まっていない学問なのです。しかし、この学問は、非常に重要であると思っています。一つには、自分を含めた人類の将来を対象として含んでいるということです。従来の学問は、いわば、自分のことを棚に挙げて自然を探求すれば済んだのですが、これからはそうはいきません。
もう一つの重要な点は、スケールの問題です。気候システムには、地球規模の大きなモンスーンという流れから、個々の雲のような小さなスケールの流れまで多種多様の現象が共存しています。これらの関係はどうなっているのでしょうか?
このような多様なものが共存しているシステムは、生命や地球環境などの複雑なシステムには共通の性質です。こうした複雑さの解明こそが魅力的な課題といえます。
このように、「気候システムの謎を解明する」ということは、実用的な観点からも、学問的な観点からも、きわめておもしろい問題です。多くの人がこの問題に興味を持ち、解明される日のくることを願って筆をおきます。
(すみ あきまさ)
|
二酸化炭素が2倍になったときに地表の温度かどのようになるかは、依然として不確定です。その理由を探るために、世界各国の研究機関のモデルによる結果か比較されました。そうすると、図10のようにある分布を示すのてすか、この差異かどこからきたのかを調へてみると、各モデルての雲の取り扱いにあることかわかってきました。図11は、各モデルについて、全地球の平均の地表温度の上昇の程度を縦軸に、雲のある領域での平均の温度の上昇の程度を横軸にとったものです。この両者の値が非常によい直線にのっていることは、地球の平均気温の上昇の変化か、ほとんど雲の存在するところの変化で決まっていることを示しています。
|